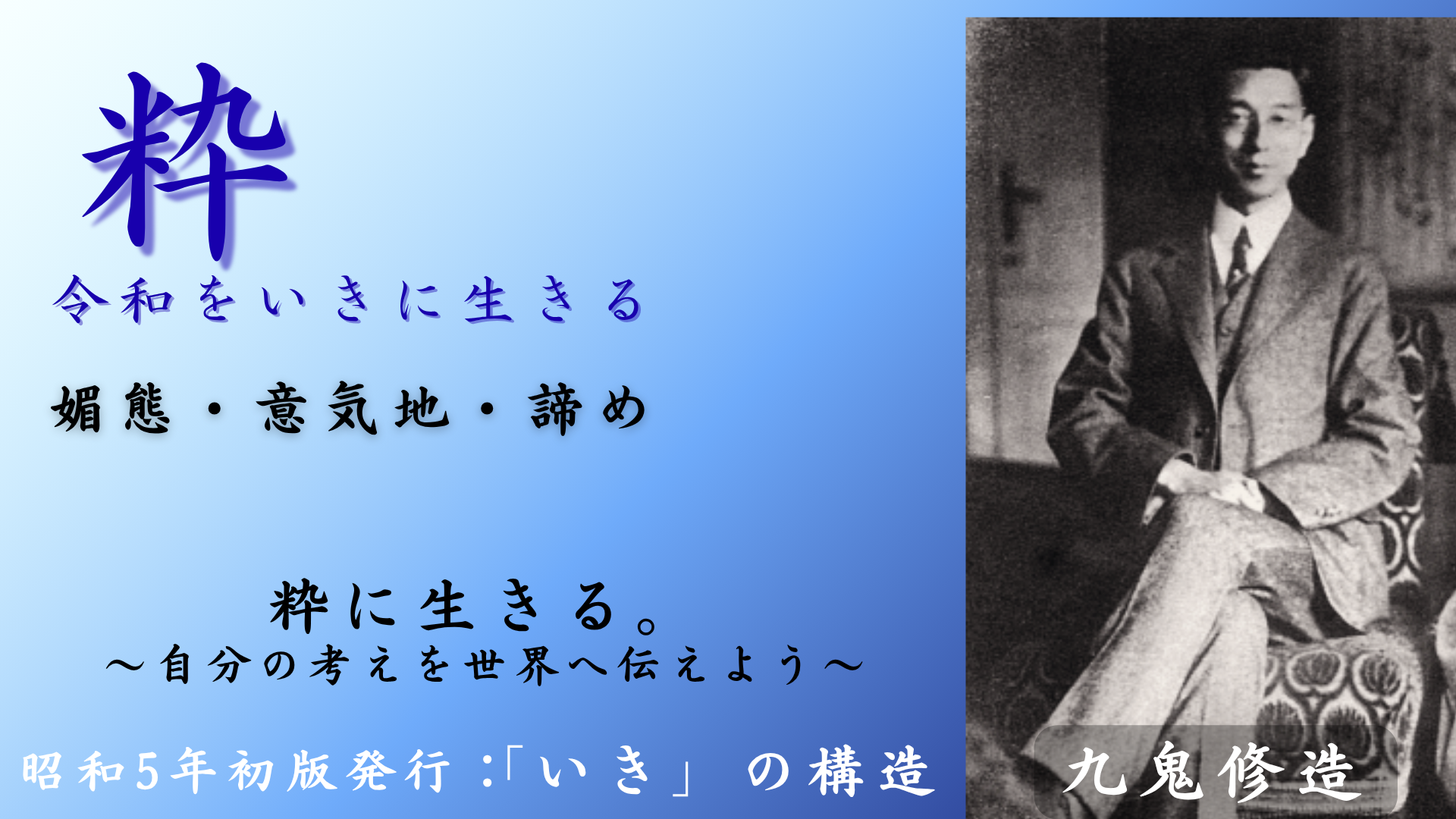「いき」とは何色か──色と光の美学
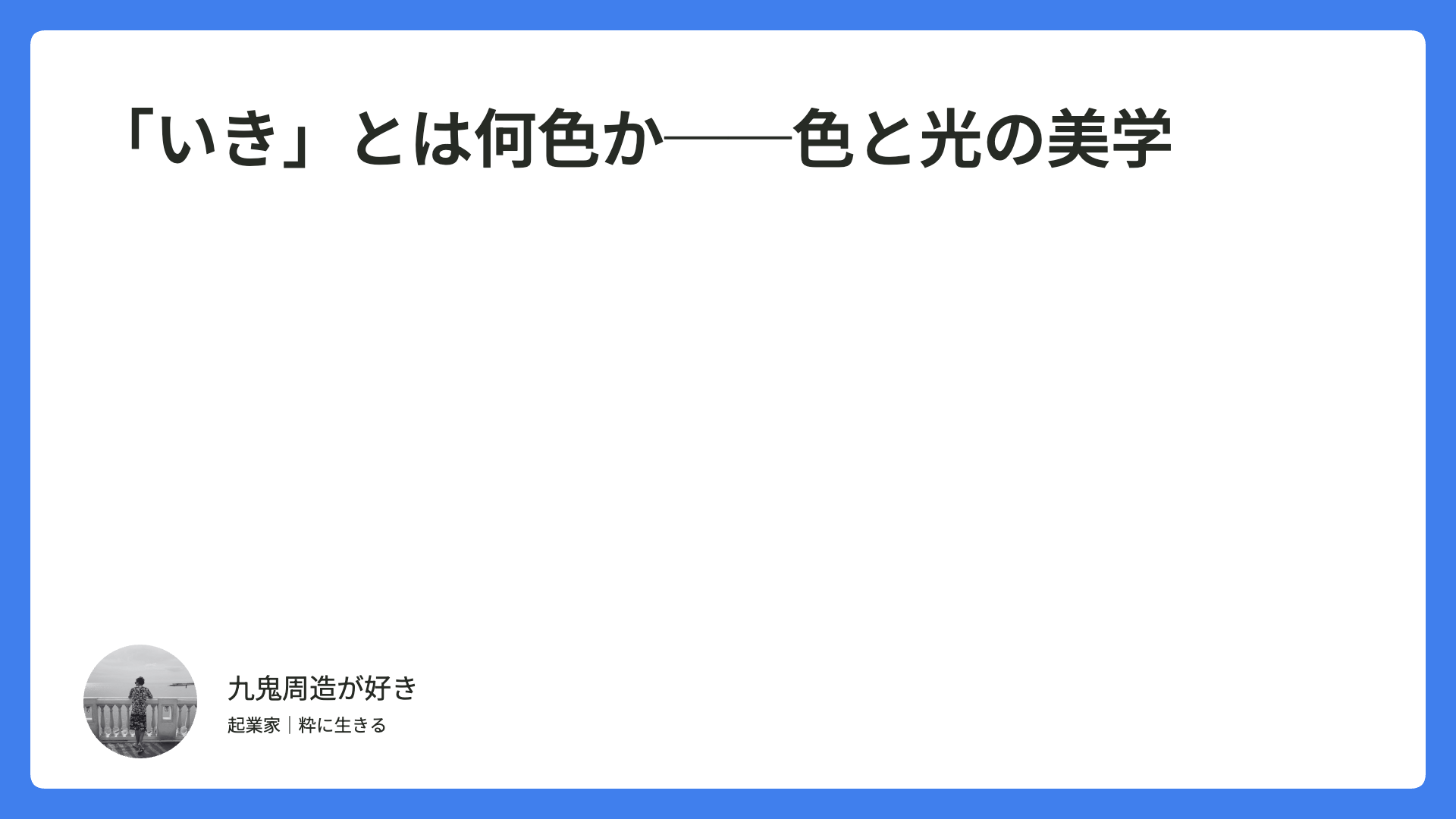
「いき」色とはなんだろうか?
江戸後期は絵具の進化とともに、浮世絵文化も発展した。
江戸の絵師達は浮世絵にその当時新しく色味を出せる藍色を重宝し、使っていた。
色は人の感情に働きかけ、文化へも影響を与える。
江戸時代の「いき」な人たちが使っていた色を見ていきたい。
色の構造と「いき」
「いき」は、決して派手な色使いではない。
江戸の人々は、模様や色においてもこの「抑制」を美徳としていた。たとえば市松模様では、「基盤の目が二種類の異なった色で交互に塗り分けられる」ことによって、視覚に奥行きを与えている。
こうした構成には必ず、控えめでいて芯の通った色の選び方がある。
「いき」の色づかいとは、二色対比、三色対比による濃淡の調和である。
色数を抑え、調和の中にかすかな差異を忍ばせるのだ。
灰色の意味──「いき」な三色
<書籍「「いき」の構造 ビギナー>の中で、粋な色として描かれているのは、鼠色・褐色・青色だ。
鼠色(灰色)──静寂と節度の象徴
灰色は、色彩の中でもっとも控えめで、もっとも多義的である。
はっきりと「赤」「青」と言える色とは異なり、曖昧さと余白を含んだ色だ。
青──記憶に残る寒色
青は「いき」の中でもっとも人気のある色の一つだった。
御納戸色、紺、藍鼠──これらの青系統は、視覚に長く残り、心の奥に静かに沈殿する。
褐色(茶色)茶──温もりと死生観
茶色は土の色であり、枯れ葉の色であり、火が消えた後の炭の色である。
つまり生と死のあいだにある色だ。
その中で江戸時代、もっとも「いき」を体現した色──それが鼠色(灰色)である。
色合いが次第に明度を減じていった究極が灰色である。
灰色は、色単体だけを取り出すと「いき」の媚態を表すのは難しい。
しかし、もう一つの要素である「諦め」を表すのには最適なのだ。
あらゆる色は明度を落としていくと、やがて灰色へと辿り着く。
その過程には、欲の抑制、装いの節度、情の深まりといった粋な価値が宿っている。
江戸の女性たちの間では、赤や黄色のような原色を、「いき」に見せるために必ず“灰み”を帯びさせていた。
それが「いきな赤」「いきな黄」である。
色彩の心理と「いき」
ではなぜ灰色や寒色系が「いき」とされるのか。
その理由は人間の視覚と心理に深く関係している。
暗い色、濃い色は網膜に長く残る。
これは「暗順応」と呼ばれる現象で、青や緑は赤や黄よりも目に残りやすい。
そのため「心に残る色」=「いきな色」とされてきた。
また、江戸の粋人たちは「明度の減少=精神性の深化」と捉えていた。
つまり「いきな色」とは、瞬間的な派手さよりも、永続的な記憶に残る静かな情熱を秘めた色。
それが寒色であり灰色なのだ。
5. 派手な色との対比──なぜ“真っ赤”は粋でないのか?
「いきな色」と聞いて、鮮やかな赤や黄色を思い浮かべる人も多いかもしれない。
だが、江戸においてそれらはむしろ“野暮”とされる色だった。
赤・橙・黄──それらは明度・彩度が高く、視覚に強く訴える。
しかしその訴えの強さゆえに、一過性の華やかさにとどまり、余韻や含みを残す「いき」にはなりにくい。
つまり、“いき”に必要なのは色の制御である。
たとえば、真紅ではなく「鳶色(とびいろ)」、山吹色ではなく「黄朽葉色(きくちばいろ)」、
どれも赤や黄の系統だが、光度を落とし、灰みを加えることで情緒が生まれる。
江戸の粋人たちは、それを感覚で知っていた。
“派手”を楽しむのではなく、“控えめ”の中に艶を仕込む。
まさに中庸な美意識が生んだ「いき」の色彩哲学だ。
6. 現代への応用──“静かな色気”をまとうということ
さて、この「いきな色」は現代でも活かせるのだろうか。
もちろん答えはイエスだ。
むしろ、情報過多で刺激に疲れた現代人にこそ、「いき」の色は効く。
モノトーンのファッション、トーンを抑えたインテリア、
“わび・さび”に通じる美意識を取り入れたデザイン──
それらは無意識のうちに、「いき」に接近している。
現代における「いきな色」とは、たとえばこういうものだろう:
- 素材の風合いを生かした深い藍
- 灰色に紫をひとしずく落としたような墨色
- 明度を落としたカーキやモスグリーン
- 使い込んだ革のような焦げ茶、赤錆色
それらはどれも、語りすぎず、ただ“そこに在る”という静けさをまとう。
それは、SNSで叫ばれる色とは対極にあるが、深く記憶に残る色でもある。
「いきな色」とは、目立つ色ではない。
中庸的だが、目立たずして魅了する力をもっている。
ぜひ、令和の現代にも品のある「いき」な色を取り得れてみてはいかがだろうか。