「諦め」──空の心で生きること
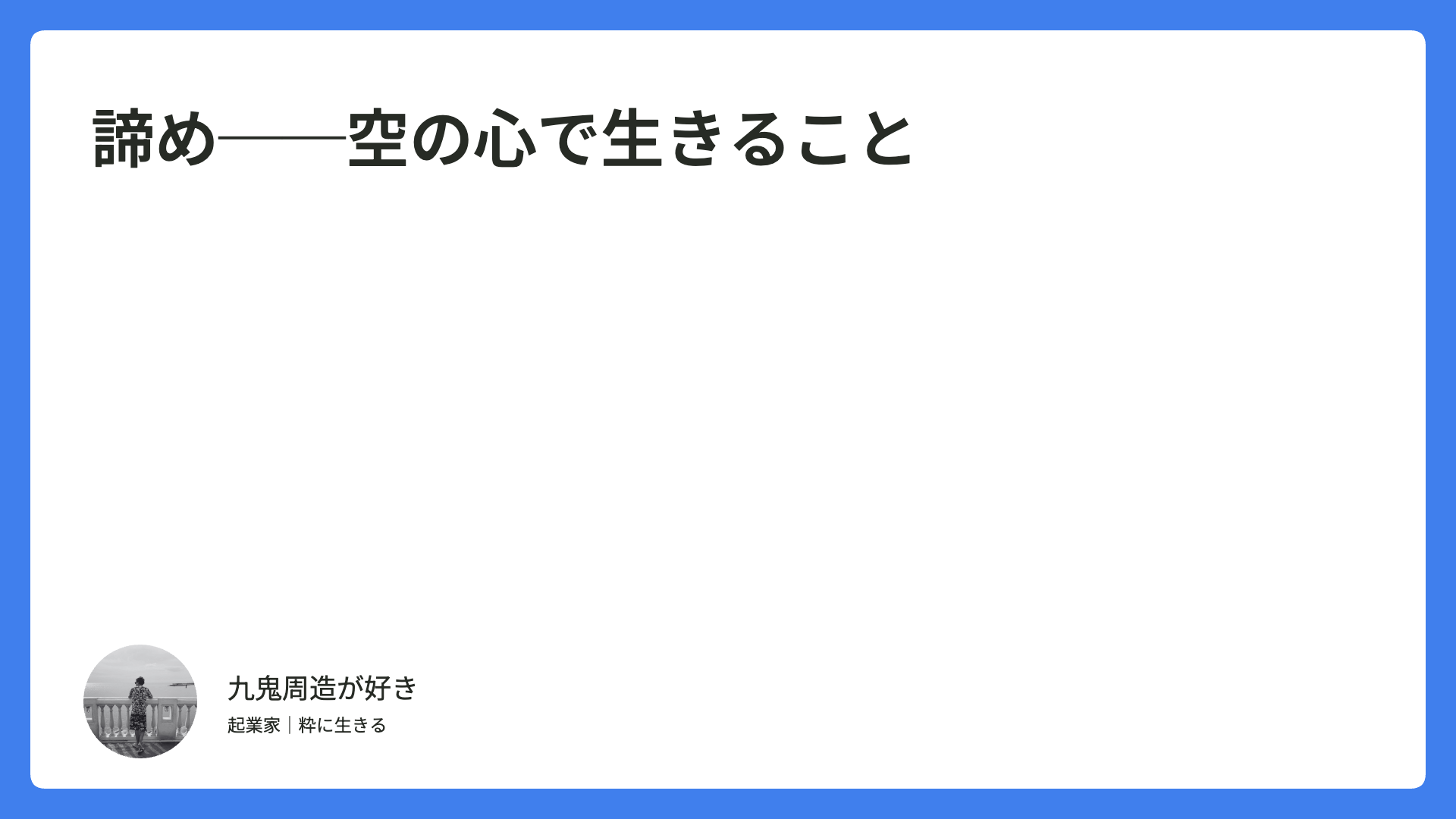
人間の欲望には際限がない。
食欲、性欲、睡眠欲、物欲、金銭欲──
「〜したい」と思った瞬間それはすでに“欲”だ。
そして、現代社会はその「欲」を原動力に回っている。
資本主義は、人の欲を燃料にして膨張し続けるシステムだからだ。
しかし、欲には終わりがない。
どれだけ手に入れても、次を欲する。
満たされたはずの心は、いつしか空虚になる。
そう気づいたとき、必要なのは
「諦め」──空の心である。
空の心──執着を手放すという強さ
「諦め」と聞くと、
「どうせダメだ」と投げやりになることを想像するかもしれない。
しかし、粋の構造の“諦め”はそういう概念ではない。
あらゆるものが移ろいゆくと知り、手放す覚悟を持つというだ。
これは仏教の空の心からきている価値観である。
「いき」の三要素のうち、この諦めはもっとも精神的であり、もっとも難しいと感じる。
縄文時代まで戻ろうとは言わない。
けれど、15年前の生活に戻ってスマホを手放すことすら困難だろう。
それでも、“なにか”を手放さなければならないときがある。
なにを大切にし、なにを諦めるか。
この選別こそが、粋な諦めなのだ。

欲には際限がありません。”足るを知る”は人に与えられるものではなく、自分自身で見つけるものなのです。
遊里で生まれた「諦め」の美学
江戸の遊女たちは、報われぬ恋を知っていた。
「私たちのような身の上では愛してくれるお客もでてこないものなのね。」
と、世を儚む想いにいたるのである。
「いき」はもともと、
沈んだまま浮かびあがることもできない、流されるままのはかない身の上。
という「苦界」(遊女のつらい境遇)から生まれたものである。
そうした試練をのりこえることによって、
すっきりと垢抜けした、未練を断ち切った、スマートな心に
達することができるのである。
だからこそ、いきはただの身だしなみではなく、
生き方の境地なのだ。
遊里の男達はどうにもつれなく、うつり気で、たちの悪い道楽者でありんす。
自分の「欲」と向き合う
無欲に生きようとは思わない。
むしろ、人は欲があるから生きていける。
だが、欲を制御できなければ、
私たちはいずれ“欲に生かされる存在”になる。
諦めとは、欲を否定することではない。
欲の連鎖を、どこかで断ち切る“空の選択”である。
・この出世、本当に自分に必要か?
・この物欲、誰かと比べて生まれたものでは?
・この恋、執着ではないか?
そう自問できる自分を育てていく。
消極的諦めではなく、積極的諦めなのだ。
意気地を持って、諦めるのでござる!
結び:「諦め」は、自由の入口である
人はなにかを諦めたとき、自由になる。
それは逃げでも、敗北でもない。
“勇気ある選択”なのだ。
空の心で、この世界をすっと通り抜けていこう。

欲を選択できてこそ、真に自由なり。
