「意気地」──自分への誇り
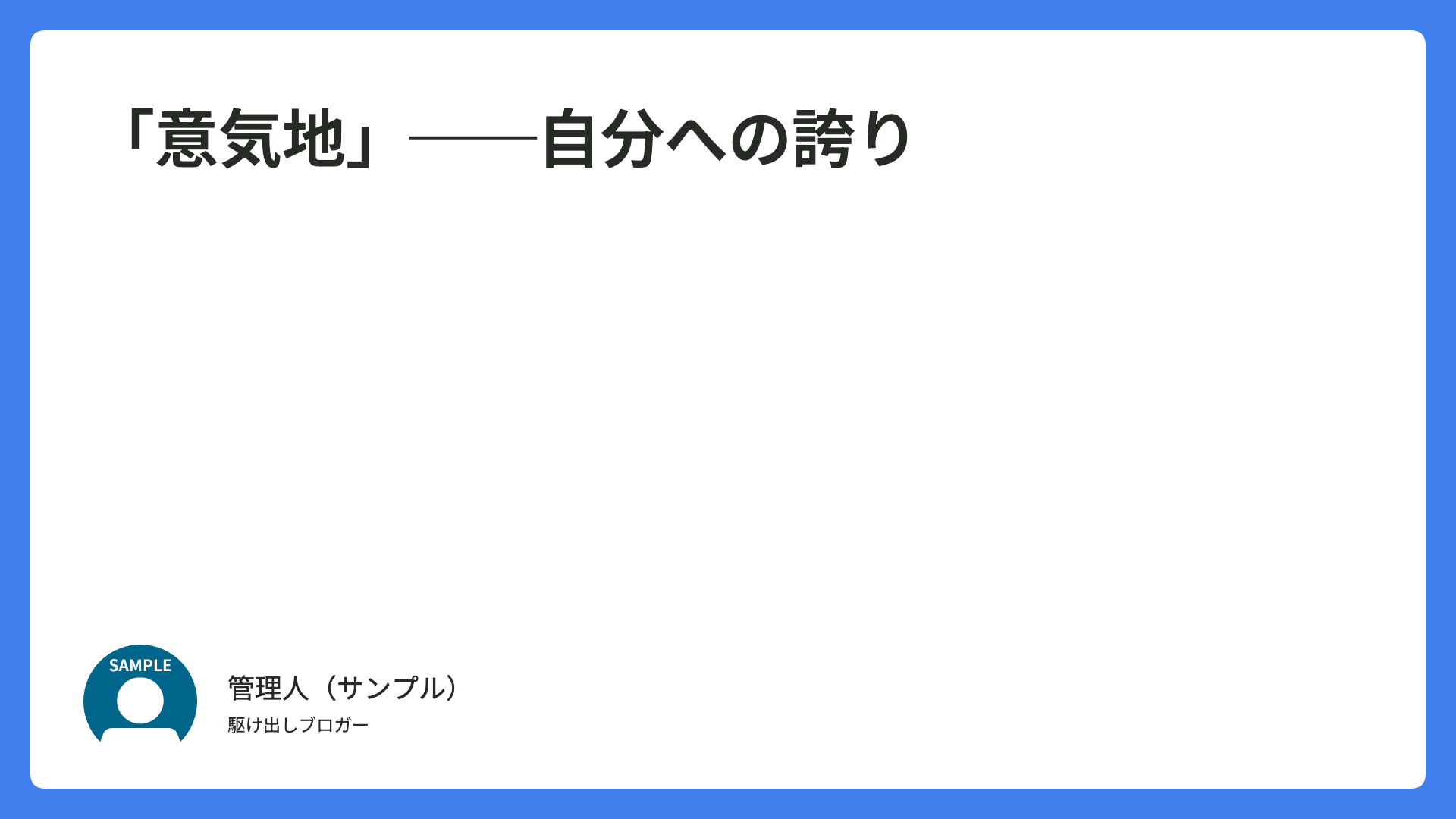
意気地なし!
と言われて嬉しい人はいないだろう。
どんなにふざけた人間でも、「おまえには意気地がない」と言われれば胸に刺さる。
この「意気地(いくじ)」とは、江戸っ子たちの気位(きぐらい)の高さを象徴する言葉だ。
プライドが高いと言うと現代ではネガティブに聞こえるかもしれないが、”pride”とは本来「誇り」を意味する。
そしてこの「誇り」こそが、粋の三要素(媚態・意気地・諦め)の中で、
令和時代──いや、資本主義に生きる現代人に最も欠けている要素ではないかと、私は思う。
意気地とは、「自分はこうありたい」という理想主義
粋には、武士道的な美学が色濃く息づいている
「武士はくわねど高楊枝」
「宵越しの銭は持たぬ」
これらの言葉は、今の合理主義から見ればただの虚勢に見える。
けれど、江戸の男たちは本気でこれを信じ、自分に恥じぬ生き方を貫こうとしていた。
媚態が“他者との関係性”に宿るなら、意気地は“自分との関係性”に宿るのだ。
人にどう見られるかではなく、自分が自分をどう見るか。
己に誇りを持たずして、何が粋でござるか。
派手な色気ではなく、黙して語る「凛」とした態度
意気地ある者は、決して騒がず、威張らず、飾らず。
静かであっても、背筋がピンと伸びている。
芸者や遊女も意気地をもって生きていた。
吉原の遊女は、どれだけ金を積まれようとも野暮な客には身を許さなかった。
「吉原の恥、吉原の名折れ」
とまで言って、はねつける気概を持っていたのだ。
金持ちでも野暮な客には身を許さなかったのである。
(粋の対義語が野暮)
つまり、「意気地」は金で買えないもの。
媚びず、流されず、自分を安売りしないという“覚悟”なのである。
野暮な客には売らへんで。金より、名や。
結び:意気地は「自分との約束」に咲く
「本当はやりたくないけど…生活のために」
「変わりたいけど…今のままで楽だし」
そんな声が心の中に渦巻くときこそ、意気地が問われているのかもしれない。
粋とは、完璧であることじゃない。
ただ、“こうありたい”と思った自分との約束を、できるかぎり守るという生き方だ。
それは苦しいかもしれない。
心の奥に一本、真っ直ぐな筋を通して生きる。
意気地を持って、誇り高くありたいものだ。
己に恥じぬよう、誇り高く生きるでござる。
